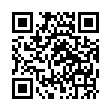今日日曜は約1ヶ月ぶりのスキー。
私、スキーは20歳で初めて16年になります。
20歳で始め、
6年目の3月に2級、
7年目の1月に1級、
8年目の12月に右足前十字靭帯断裂、
9年目の1月に左足内側側副靭帯損傷、他...
と、スキーにまつわる話題はいろいろ^^;
それはさておき、今日は岐阜県飛騨地方にある「鈴蘭高原スキー場」へと足を運んできました。
混雑無し! リフト待ち無し! 往復路の渋滞皆無!
スキー場としては売り上げが伸びず大変だとは思いますが・・・
奥に見えるのは標高3,000m超の「乗鞍岳」です。
ゲレンデ上部からは北アルプスをはじめ、乗鞍岳、木曽御岳、南アルプスと、絶景の眺望が広がります。

ちびっこゲレンデには専用のの動く歩道(約50m)があります。
そりの子供さんも十分に楽しむことが出来ます。

これだけの設備があるのに、客入りが少ないのは「もったいない」のひと言です。
同じ岐阜県でも奥美濃地方のスキー場は、東海北陸自動車道のおかげで、関西方面から随分な客入りがあるようですが、飛騨地方のスキー場が奥美濃の手法を見習っても、高速道路網というインフラや、今まで行ってきた販売(広告)戦略によるイメージ付けが大きく異なるので、おそらく期待するほどの効果は得られないのではないかと思います。
スキー人口のみならず、ボード人口も減少傾向にある昨今、飛騨のスキー場が今更遠方のお客へ多大な広告宣伝費を掛けた戦略を打って、どれほどの効果があるのかは疑問です。
それよりも、岐阜県内のお客さんに「飛騨のスキー場」の「良い部分」を、需要に合った形で分かりやすく見せることでも、収支が合うに十分な集客が期待出来るんじゃないかなぁと思います。
「県内客」を誘客出来れば、経営上十分な客数を確保できるのではないかと思うのです。往復路の渋滞が殆ど無い飛騨地方のスキー場は、時間的に奥美濃のスキー場よりも近いはず。帰路の疲れが少ないです。
鈴蘭高原スキー場は東海ラジオ系列ですから、系列会社を広告媒体としてだけではない方法でのメディア活用を行えないものかなぁ・・・
私自身、混雑したスキー場は何より「大嫌い」なのですが、それよりも気に入っているスキー場自体が無くなってしまわないよう願うばかりです。
心地よい冬空の下での楽しさは非日常で、私は大好きです。
今日、多治見市のとあるタイル工場へお邪魔しました。
そこで見たのが、恐ろしいほどの
在庫の山!!。

長年の仕事の結果に出来てしまった在庫の山だそうです。
どうでしょう・・・倉庫面積は1,000平米以上あるでしょう。その中がすべて
動かない在庫!
これは商売人としては本当に怖いことです。
だって、作業場所が狭くなってしまう上に、売れずに残った製品が財務上の資産として計上されてしまうんですよ!
この在庫、とにかく「タダでいいから使ってください!」との声。
同じ商売人として聞かなかったフリは出来ません。
今日、私の知りえる範囲の建築施工業者さんに声を掛けています。
「使えるものはタダで持って行って!」って。
動かない在庫とはいえ、世界最高品質の「日本製」タイル。
凍結融解試験、吸水試験、滑り性試験、含有物の分析試験などなど、日本製を日本で使ってもらうための厳しい品質基準をクリアしてる製品。
日本製は中国製他外国製など目では無いです。品質は比べ物にならないんです!
これほど良い製品が産業廃棄物として廃棄されてしまうのは残念です。
日本のものづくり精神に反していると思います。
良いものは「何らかの方法」で認められて、使われるべきです。

製造屋さんが「タダでもいいから使って欲しい」、また施工屋さんは「良いものを安く使いたい。
ここにはお客様へ「良い製品」を「より安く」提供する方法がありそうです。
樹木の生命力には、本当に驚かされることがあります。
「痛い!」なんて訴えることも無いですし、適切な飲み薬や塗り薬があるわけでもないので固有の治癒力なのですが、それでも「自己回復能力」があるのには今更ながら感心します。
傷を負った直後の様子。

かなりの広範囲に樹皮が剥がれてしまっています。放っておくと根元が腐ってしまう可能性が・・・
で、3年後の様子。

樹皮の再生が進んで、傷口が小さくなっています。治癒力って凄いですね。
細胞分裂の妙技には、本当に驚かされます。
でも、傷が付いたまま放っておいても直りません。
放っておくと、むき出しの木質部がどんどん
腐ってしまいます
少しだけ手間を掛けて傷の治りを早くするのが、私たち人間が出来る最善の処置です。
早めに見つけて、早めに処置する、人間の病気や怪我と同じです。
造園屋さんの仕事は単に木を植えるだけではない、木々の健康管理も造園屋さんの仕事・使命だと思っています。
現在までに作られた緑地緑化を如何にして維持していくか、また今までの緑化の問題点を洗いなおして、次の時代には従来よりも「より良い」緑化を築くことが、造園屋さんのこれからの仕事ではないかと思っています。
でも、手間代ばかりで材料仕入れの無い仕事を嫌う業者さんが多いのも、残念ながら事実なんですよねぇ・・・
昨日は、可児市から頂いた工事の完成(竣工)検査がありました。
検査といっても殆ど「不合格」になることは無いんですね。これが。
工事の段階ごとに、発注者さんが規定する規格に合格しているかどうかの測定他検査を行っていますから、完成(竣工)検査の時点で
「× 不合格」
ってことは無いのです。
道路工事なんかで黒板を使って写真を撮っている検査。見たことありません?
。
じゃぁ、なんで完成検査?
税金で工事を発注している側の責任として、部分的な抜きとり検査を行って、受け入れる確認を行っているんです。
条件は、発注内容=完成内容です。
(発注内容≠完成内容では、受け取れる筈がありませんよね)
一般の方々には意外と知られていないんですが、役所他公共機関が発注する仕事は、現場が出来ているのは当然ですが、それ以上に「書類」がきちんと作られて揃っているか、こちらも大きなポイントです。
これがまた結構な量で、場合によってはダンボール一箱くらいは必要になります。
書類が揃っていないと、
現場を受け取ってもらえません。
完成検査の日程も決めてもらえません
現場もさることながら、書類作成にも相当な時間・日数を費やさなければならないんです。
現場も書類も毎回きちんと作っているんですが、いざ「検査」っていう言葉を聞くと、ちょっと
緊張・・・
してしまいます。